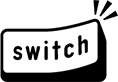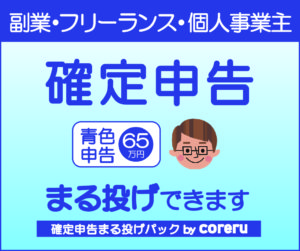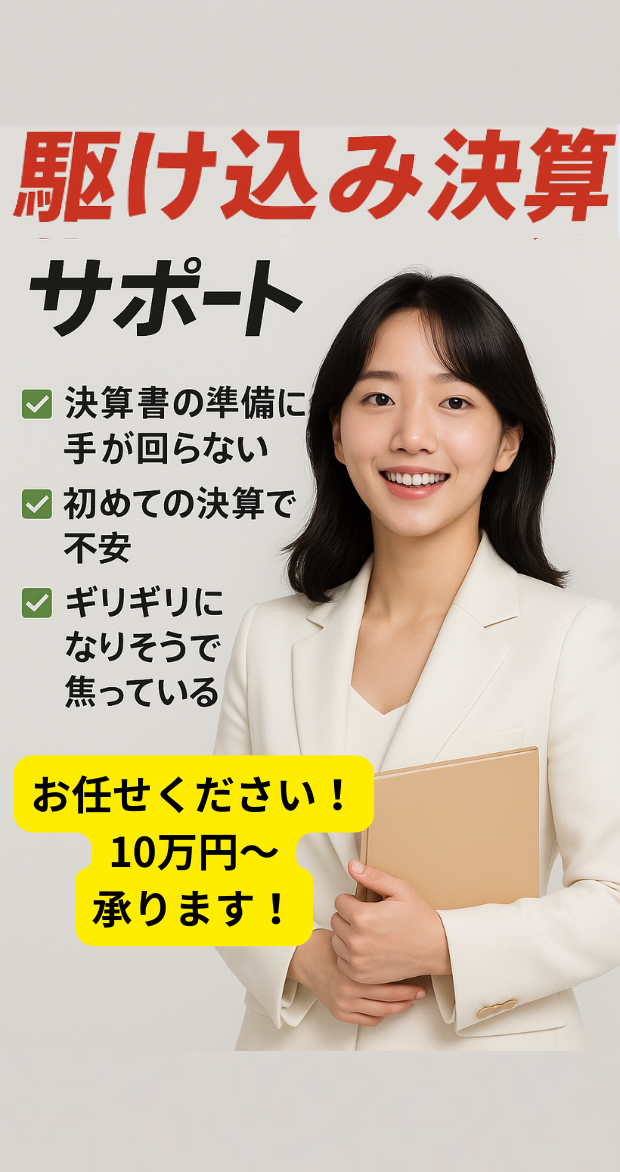基礎控除とは、ほかの控除のように一定の要件に該当する必要がなく、一律に適用される控除です。
確定申告や年末調整において、所得から差し引くことができ、所得税と住民税を少なくすることができます。
ここでは、確定申告時における基礎控除のポイントをお話します。ぜひ参考にしてください。
※令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)からは基礎控除が改正になりますのでご注意ください。
参考:個人事業主の確定申告ガイド|フロー図を用いてわかりやすく解説
もくじ
0. 【改正】令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)からの基礎控除のポイント
【令和1年度(2019年1月1日~12月31日) 確定申告はこちらから】
1. 基礎控除のポイント
2. 38万円と33万円の基礎控除の違い
3. 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
4. 基礎控除は所得のある人に一律に適用される
5. 確定申告関連リンク
0. 【改正】令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)からの基礎控除のポイント
令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)から基礎控除額が改訂になります。
- 所得税の基礎控除額が38万円→48万円になる(住民税の基礎控除額は33万円→43万円)
- 合計所得が2,400万円を超える場合は、32万円、16万円と段階的に控除額が少なくなる。(住民税の基礎控除は29万円、15万円)
- 合計所得が2,500万円を超える場合は、基礎控除額は0円。
所得税の基礎控除(※確定申告で記入する金額はこちら)
| 個人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
住民税の基礎控除(※確定申告で記入しません)
| 個人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
1. 基礎控除のポイント
基礎控除のポイントは以下のとおりです。
- 基礎控除には38万円と33万円の二種類がある
- 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
- ほかの控除のように一定の要件に該当する必要はなく、一律に適用される
以下から詳しくご説明します。
2. 38万円と33万円の基礎控除の違い
基礎控除には、38万円と33万円があり、違いは以下のとおりです。
・38万円…『所得税』の計算に用いる基礎控除額
・33万円…『住民税』の計算に用いる基礎控除額
上記のとおり、38万円は所得税の計算に用いる基礎控除額で、33万円は住民税の計算に用いる基礎控除額となります。
もしあなたの給与がパート収入のみ(給与所得だけ)の場合、基礎控除38万円と、給与所得控除65万円を足した103万円を超えた場合に所得税が課税されます。
しかし、住民税の場合は基礎控除が33万円ですので、33万円に65万円を足した98万円を超えた部分が住民税の計算対象となります。
つまり、パート収入が103万円であった場合、所得税はかかりませんが、98万円を超えた5万円に対しては住民税がかかるというわけです。
ただし、住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっています。
住民税の非課税控除額とは、住民税を課税するかしないかを判断する際に使われる金額です。
つまり、パート収入の場合、35万円に65万円を足した100万円までは住民税が非課税ということになります。
住民税は、課税を判断する金額と、実際の計算で使われる金額が異なるため注意が必要です。
3. 確定申告書類に記入する基礎控除額は38万円
確定申告書に記入する基礎控除額は38万円になります。
具体的には以下のとおりです。
【確定申告書A】
第一表…所得から差し引かれる金額の(15)基礎控除に38万円と記入します
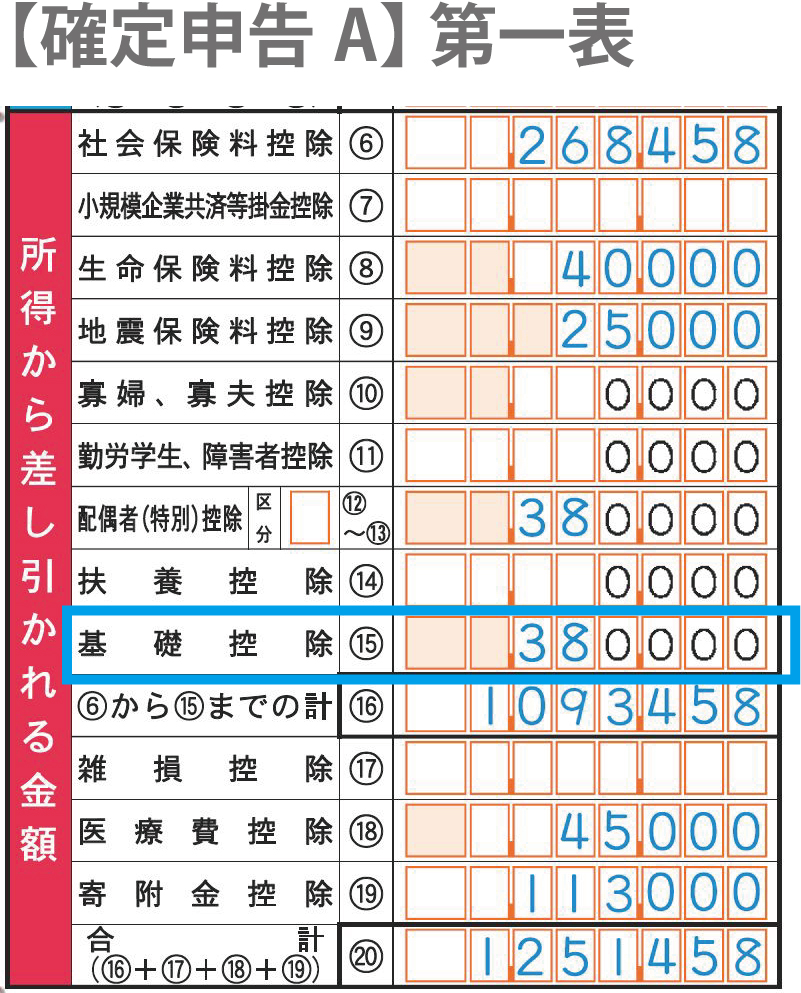
【確定申告書B】
第一表…所得から差し引かれる金額の(24)基礎控除に38万円と記入します
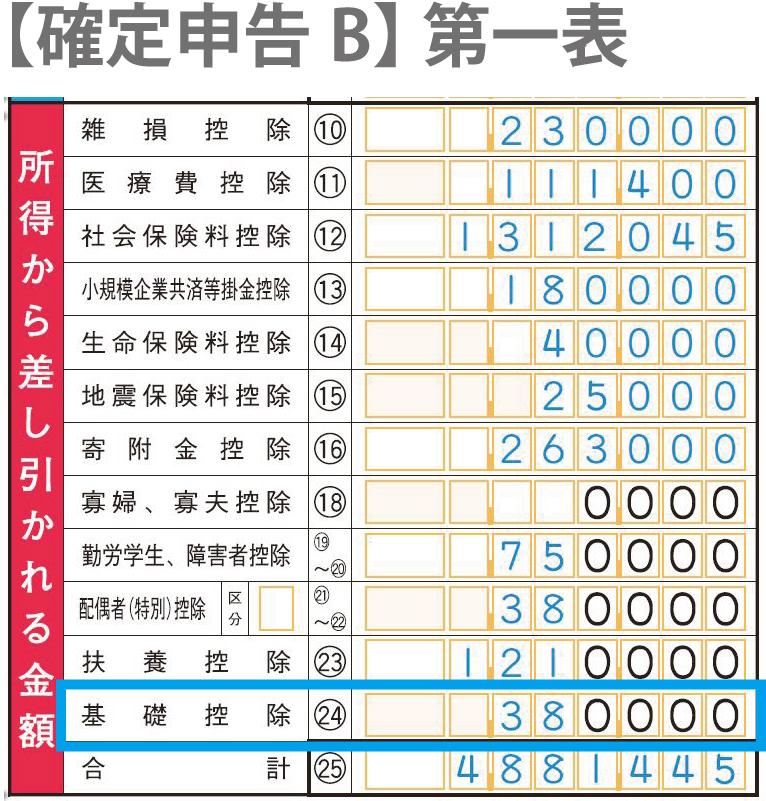
確定申告書では、33万円の基礎控除額を記入するところはありません。
確定申告書を提出する場合は、住民税の申告は必要なく、市区町村が確定申告書等を元に課税計算します。
4. 基礎控除は所得のある人に一律に適用される
基礎控除は、ほかの控除のように一定の要件に該当する必要はなく、所得のある人すべてに一律に適用されます。
ネットでの申告の場合は基礎控除額38万円は入力されていますが、手書きの確定申告書類には記入されていません。
手書きの確定申告書類にも忘れずに記入しましょう。
5. 確定申告関連リンク
・個人事業主の確定申告ガイド|フロー図を用いてわかりやすく解説
・副業の確定申告ガイド|20万円超から始める手順やバレないやり方
・フリーランスの確定申告|押さえたい8つのポイント
・【2019年度確定申告】改正|基礎控除38万円と33万円完全攻略
・【2019年度確定申告】生命保険料控除の完全攻略ポイント8つ
・【2019年度確定申告】社会保険料控除の完全攻略ポイント8つ
・【2019年度確定申告】寄付金控除の完全攻略ポイント5つ
・【2019年度確定申告】青色申告特別控除の完全攻略ポイント9つ
・【2019年度確定申告】専従者給与・専従者控除の攻略ポイント
・【2019年度確定申告】65万円青色申告特別控除を受けるためのポイント
・【2019年度確定申告】扶養控除の完全攻略ポイント5つ
・【2019年度確定申告】配偶者控除の完全攻略ポイント5つ
・【2019年度確定申告】配偶者特別控除の完全攻略ポイント6つ
・【2019年度確定申告】医療費控除の完全攻略ポイント8つ
・はじめての確定申告の必要書類まとめ・画像つき
・[確定申告]住宅ローン控除の必要書類の集めかた画像つき
・年末調整と確定申告の違いと両方対象者のための4つのケース
最後に
いかがでしたでしょうか。
基礎控除は所得のある人に一律に適用される控除ではありますが、所得税と住民税の計算において違う点があるため注意が必要です。
しっかりポイントを押さえましょう。